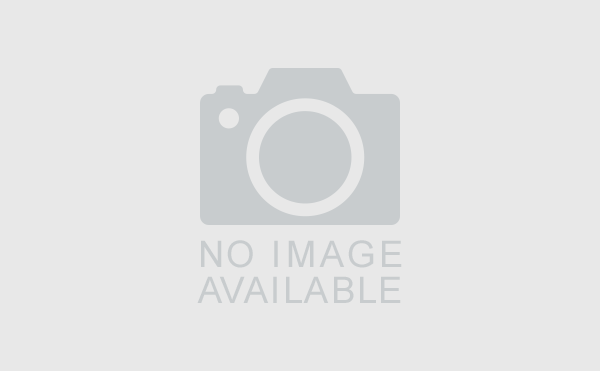この人に聞く 西澤真美子さん「詩人・坂村真民の世界」

長原眞
「『生命の光』誌の読者に、坂村真民(しんみん)という秀(すぐ)れた宗教詩人があります。この人の多くの詩を魅せられるように読んだこと、幾たびでしょう」(手島郁郎)
〈1972年『生命の光』259号より〉
タンポポ魂
踏みにじられても
食いちぎられても
死にもしない 枯れもしない
その根強さ そしてつねに
太陽に向って咲く
その明るさ わたしはそれを
わたしの魂とする真民

二度とない人生だから
二度とない人生だから
一輪の花にも
無限の愛を そそいでゆこう
一羽の鳥の声にも
無心の耳を かたむけてゆこう真民

真実一路に生きた詩人の言の葉に、心が揺すられます。私は、真民先生の詩に親しむうちに、こんなに人の心を打つ詩は、どういうところから生まれてくるのだろう。坂村真民という詩人は、どんな人なのだろう。そんな思いをもつようになりました。そして、いつの日か愛媛県砥部町(とべちょう)の「坂村真民記念館」を訪ねたい、と願ってきました。
昨年、機会を得て、記念館を訪れました。そこには坂村真民先生の三女の西澤真美子さんが、和服姿で出迎えてくださいました。
真言碑「念ずれば花ひらく」
長原眞 今日は、わざわざ時間を割いてくださって、ありがとうございます。
実は、私は1週間前、北海道の稚内(わっかない)を訪れました。その時、知人の案内で、大徳寺というお寺に建てられている、「念ずれば花ひらく」という坂村真民先生の真言碑と、その元になった直筆の書を見せていただきました。その書からは、あふれる生命を感じました。
西澤真美子 父は練習しないで、全身全霊、念を込めて書いたと思うんです。生きた字であって、それを石に彫ったら、それが生きる石になるのですね。
長原 そのお寺の住職さんが、「檀家(だんか)には、樺太(からふと)から引き揚げてきた人たちが多いです。この海の向こうは樺太です。望郷の想いを抱きながら亡くなられた方々の弔いのために、この碑を建てました」と言われます。
西澤 そうですか。父は若い時に朝鮮へ渡り、高等女学校で教えていました。
向こうに骨を埋(うず)めるつもりでしたが、日本が戦争に敗けたので帰ってきました。ですから、そういう人たちの気持ちは、きっとわかると思います。
真実の人間になるため
長原 真民先生の詩は、だれにもわかるような言葉で、しかもとても深い心が感じられます。「そうだ、私もそう生きよう」という力を与えられます。

西澤 父は、最初は短歌に打ち込んでいました。でも、短歌に親しんでおられるのは、ある程度、教養のある方々です。そういう短歌に満足できなくて、父の表現では、普通のおじさん、おばさんが見てくれるようなもの、そして、生きる力を与えるような詩を書きたい、と言っていました。
長原 私が感動し、教えられるのは、真民先生の詩作へのひたぶるな姿勢です。詩が生まれる前の、根源の世界に迫ろうとする気迫です。私も『生命の光』誌の編集に携わっています。及び難いことですが、少しでも根源の世界から霊感を汲みたい、と心がけています。
西澤 父は午前3時ごろ起きて、近くの重信川の川辺に下りて、お日様の出るのを見ながら祈るのです。教師を辞めて詩一筋になった65歳以降は、0時に起床していました。朝日の光を吸ってエネルギーをもらう、これが長生きできた大切なことだったと思います。
父はよく、「夜が明けて詩を作る人はたくさんいるけれど、ぼくの詩は未明混沌(こんとん)の中から生まれてくる」と言っていました。すべてが生まれ出る前の未明混沌の世界を、大切にしていたのだと思います。
最初のころに出版した詩集の扉に、「真実の人間になるために詩を書く」と記しています。詩人になるためではなく、真の人間になるために詩を書いてきた。
私が小さい時に見た父も、95、96歳の晩年の父も、変わらないですね。変わらないというのは、見ている先が変わらないからでしょう。
父の詩の中で私が好きなのは、最初の詩集『六魚庵天国』の「六魚庵箴言(しんげん)」です。
その一
狭くともいい
一すじであれ
どこまでも掘りさげてゆけ
いつも澄んで
天の一角を見つめろ
その二
貧しくとも
心はつねに
高貴であれ
一輪の花にも
季節の心を知り
一片の雲にも
無辺の詩を抱き
一碗の米にも
労苦の恩を思い
一塊の土にも
大地の愛を感じよう真民

いのちの光をかかげて
長原 手島郁郎との出会いについてですが、真民先生が友人から紹介されて『生命の光』を読んだ時の驚きを書いた手紙が、私たち幕屋の機関誌に載りました。
「私は『生命の光』を拝見して、こんな光と生命に満ちあふれたものは今までに読んだこともなく、触れたこともなく、全く感動いたしたのであります。
私は、仏陀(ぶっだ)の道を歩んできた者でありますが、私が大詩霊さま、と呼んでいるのは釈尊であり、イエス・キリストであります。そういう意味で、私は世間一般の仏教徒とは違った道を歩いてまいりました。
大詩霊としてイエス・キリストの光を仰ぎ慕う者であります。”生命の光” こそ、私の祈願であります。
私の詩誌『詩国』は地上の天国であり、神仏の念願である『平和の国』であります。『生命の光』と同じ意味であります。
火の国の火を受け継がむ
わが願ひ 導きたまへ光かかげて
詩人」
坂村真民先生も手島郁郎も同じ火の国・熊本の出身です。2人の親交は、最初の出会いからお互いを尊び合い、最後まで続きました。
西澤 私も『生命の光』を読ませていただいていますが、手島先生は仏教にも造詣(ぞうけい)が深いですね。それこそ宗教宗派を超えてのお交わりだったと思います。
多くの人のために祈りつづけてきた父の晩年に、天から臨んだ啓示は「大宇宙大和楽」という言葉でした。生きとし生けるものすべてが和楽する平和な世界、それが父の目指した究極の世界だったと思います。色紙に「すべてに愛を」と書いて人に差し上げていました。
長原 今日は、貴重なお話を伺い、ありがとうございました。
*
記念館には、坂村真民先生の詩や、発刊された詩集、評論、自筆の書が、年代順に陳列されており、多くの若者や親子連れの来館者でにぎわっていました。
来館者の感想を記すノートには、「かつて人生に行き暮れていた時、真民さんの詩に出合って生きる希望と力を得ました」といった、感謝の言葉が多くつづられていました。
真美子さんから頂いた真民先生の詩集の扉に、こう書いてありました。
体のなかに
真美子
光をもとう
父にかわり

坂村真民記念館
「人はどう生きるべきか」の心が伝わる詩や墨書を展示。2025年3月2日まで企画展「真民さんとタンポポ」が開催されている。愛媛県伊予郡砥部町。
本記事は、月刊誌『生命の光』863号 “Light of Life” に掲載されています。