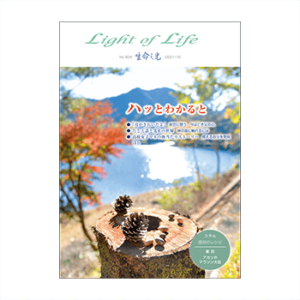聖書講話「たとえ話と実在の世界」ヨハネ福音書16章25~30節
聖書の中には、イエス・キリストによって語られた、神の世界についての多くのたとえ話が収められています。目に見えない実在は、理論的な話では伝わらず、たとえ話をもってハッと悟らせる以外にないからです。
この講話では、キリストが世を去る前夜に語られた「最後の遺訓」を通して、たとえで語られた意味とその背後の世界に触れる信仰が説かれています。(編集部)
「わたしはこれらのことを比喩で話したが、もはや比喩では話さないで、あからさまに、父のことをあなたがたに話してきかせる時が来るであろう。その日には、あなたがたは、わたしの名によって求めるであろう。わたしは、あなたがたのために父に願ってあげようとは言うまい。父ご自身があなたがたを愛しておいでになるからである。それは、あなたがたがわたしを愛したため、また、わたしが神のみもとからきたことを信じたためである。わたしは父から出てこの世にきたが、またこの世を去って、父のみもとに行くのである」
ヨハネ福音書16章25~30節
弟子たちは言った、「今はあからさまにお話しになって、少しも比喩ではお話しになりません。あなたはすべてのことをご存じであり、だれもあなたにお尋ねする必要のないことが、今わかりました。このことによって、わたしたちはあなたが神からこられたかたであると信じます」
今日で、イエス・キリストの「最後の遺訓」の学びを終わります。
「わたしはこれらのことを比喩で話した」とありますように、イエス・キリストは人々に神を教えるのに、いつも比喩やたとえをもってなさいました。真理は元来、たとえでしか語れないものです。わけても神様という天の存在や、人間界とは別格の神の国を、体験したことのない者に理解させるのは、至難の業(わざ)です。
ここで弟子たちが、「もう比喩では話されません。だれもあなたにお尋ねする必要はありません」と言って、わかったつもりになっています。けれども、説明を聞いて「ハハー」と独り合点したとしても、それで神の国に入ったわけではない。信仰にとって、早わかりすることがいちばん困る。私たちは、いつまでも求道者であるときによいのです。
説明では実体は伝わらない
ここでいう「比喩」は、原語では「παροιμια パロイミア」で「παρα パラ そばに」と「οιμος オイモス 道」という語の複合語です。道自体ではなく、道のそばに、ということです。ですから、たとえ話や比喩というのは、ある実在の真実を説明するために、そのそばのことまでは語れるけれども、実在自体を示すということはありません。それ自体を酌(く)み取るのは一人ひとりの信仰です。見抜く力がない人は、たとえ話をどれだけ聞いても、その周囲をぐるぐると堂々巡りするだけであって、その実在にタッチするということはない。
戦国時代の武将・伊達政宗(だてまさむね)は、東海道を通って駿河国(するがのくに)に着いた時、
見ぬ人の問はば如何(いか)にと語りなむいくたび変はる富士のけしきを
と詠(うた)いました。富士山は朝昼晩、また四季それぞれに景色が変わります。
「富士山はどうでした」と見たことのない人から聞かれて、「富士とはこうです」と三角形の山を示しても、それは富士山とは違います。また、朝日に映える富士山と、夕暮れ時に紫色や紅色(くれないいろ)に輝く富士山とでは違って見えます。それで、「紫富士」とか「紅富士(べにふじ)」とか、富士山にいろいろな名前をつけるけれども、それは、その時その時の瞬間的な情景であって、富士山それ自体ではありません。では、説明がつかないから富士山がないのかというと、そうではありません。

そのように時々刻々変わってゆく世界、生きた世界は言葉で説明ができません。説明するにしても、それはたとえで説明するのであって、たとえの域を越えることはできません。
富士山でもそうであるならば、まして神様というものを、今のキリスト教の神学者のように、「神とは、かくかく、かくなるものである」と定義して、「定義を信ぜよ」というのは、とんでもないことです。そして、いまだ神を知らない者が、神についての定義をいっぱい覚えて、「ハハー、それらを組み立てたら、このようになるのだな」などと思うなら、それは自分の頭脳が組み立てた神様であって、真の神ではない。それは教理を信じているのであって、実在する神に出会ったという経験を欠いでいます。
心に響くたとえ話
イエス・キリストは福音書の至るところで「神の国とはかくのごとし」と言って、神の国について、また信仰について定義や理屈ではなく、比喩やたとえで語られました。
ある時、律法学者がキリストに「何をしたら永遠の生命が受けられますか」と尋ねました。聖書には「神を愛せよ。また自分のように隣り人を愛せよ」とあります。それでその律法学者は「では、私の隣り人とはだれのことですか」と言います。隣り人がだれかわかれば愛せる、というわけです。するとキリストは、「善きサマリヤ人の話」をされました。
ある人がエルサレムからエリコに下ってゆく道すがら、強盗に襲われ、着物をはぎ取られ、打たれて傷つき倒れた。そこへ祭司やレビ人というユダヤの宗教的な人々が通りかかったが、見て見ぬふりをして行った。ところが、当時ユダヤ人から嫌われていたサマリヤ人の一人が通りかかり、その人を見ると放っておけずに、その場で介抱し、宿に泊めてあげた。そればかりか翌日、宿屋の主人に持ち合わせたお金を渡して、「これで足りないなら、帰りにまた支払うから、どうぞ介抱してやってくれ」と言って立ち去った。
「その傷ついた旅人にとって、隣り人はだれだったろうか」とキリストが問われた時に、その律法学者は、「その旅人を介抱した人です」と答えざるをえませんでした。
「隣り人とはだれか」という問いに対してキリストは、「隣り人についての定義など知らない。愛された者にはだれが隣り人であったかがよくわかるのであって、『隣り人とはだれか』と問うことすら間違っている。まして、『私は愛を実践している』といって意識して行ない、うぬぼれるなら、それは愛でない」と、たとえを通して言わんとされるのです。
新しい真理を伝えるために
このようにイエス・キリストが、ご自分の宗教をすべてたとえで語らなければならなかったというところに、キリストの宗教の特徴があります。
「新しい酒は、新しい皮袋に入れなければならない」とキリストがおっしゃったように、キリストの宗教は新しい酒なのであって、弾力のある新しい皮袋に入れ、新しい形式でもって示す以外にないのです。しかもその新しい宗教は、今までだれも、見たことも聞いたこともない、質的に全く新しいものです。
神の国という、まだだれも味わったことも見たこともない、全く新しい宗教的世界、それを学ぶ私たちが早合点して、「ああ、こうなんだ」と言葉の定義だけを覚えて、わかったように思うならば、とんでもないことです。そこに西洋神学の錯覚がある。見たこともない、新しい実在に対しては、私たちは襟を正して学ぶ態度が必要です。
先日、台湾に行った時、暑かったので、皆でジュースを飲みました。ある人はマンゴージュースを頼んで「うまい」と言って飲みましたが、私は一口味見して混ぜ物だと思った。昔、家族が台湾に住んでいた時に、マンゴーをよく食べたものですからね。でも、本物のマンゴーを食べたことのない人は、「これがマンゴーだ」と思ってしまうわけです。
本物に触れる、実在に触れるということと、実在に似たものに接するということは、別のことです。せめてほんとうに神を知っている人が、「神の国はこうなんだ」と、天のことを地上の言葉に翻訳し、地上の卑近なたとえを引いて語る以外にありません。その時に、ハッと私たちの心が開かれて、神の国に躍り入ることができるのです。
ですからキリストは、マタイ福音書13章で「彼らにはたとえで語るのである。それは彼らが、見ても見ず、聞いても聞かず、また悟らないからである」と語っておられます。頑(かたくな)な心の人は、キリストの語るたとえ話がわかりません。それでキリストは、「聞く耳ある者は聴くべし」と言われるのです。わかる者はわかる。わからない者はわからなくてもしかたがない。真理を聞く耳のない者にどれだけ聞かせてもだめだ、というわけです。
that(あれ)から this(これ)へ
25節でキリストは「わたしはこれらのことを比喩で話したが、もはや比喩では話さないで、あからさまに、父のことをあなたがたに話してきかせる時が来る」と言われました。
それはどういう意味でしょうか。ヨハネ福音書15章や16章には、「父のみもとから来る真理の御霊がくだる時、それはわたしについてあかしをするであろう」とか、「真理の御霊が来る時には、あなたがたをあらゆる真理に導いてくれるであろう」とあります。
その「真理の御霊」と称せられる神の霊が私たちに臨むまでは、私たちに真理はわからない。たとえわかったと思っても、それは独り合点です。また、私たちが頭でどれだけ考えましても、神はわかりません。けれども、イエス・キリストに流れていた神の生命が人間に臨む時に、ことごとく真理がわかる時が来る、というのです。
ここで、「真理の御霊がくだる時、それはわたしについてあかしをするであろう」とある「それ」は、ギリシア語原文では「εκεινος エケイノス」で、英語なら「that あれ」という意味です。
ところがペンテコステの日(※注)に、聖霊が120人の者にくだった時、皆が驚くべき霊的経験に入りました(使徒行伝2章)。その時ペテロは、「イエスは神の右に上げられ、父から約束の聖霊を受けて、それ(これ)を私たちに注がれたのである」と語っております。ここにある「それ」は、「τουτο トゥート」というギリシア語で、英語なら「this これ」です。すなわち、キリストから「あれが来たらわかる」と言われた時は、弟子たちにとって神様はまだかなたのこと「that」でしかなかった。聖霊の経験をしない間は、神は遠い「that」の存在、彼岸の存在です。ところが、天上の世界の御霊が弟子たちに流れくだった時に、「that」ではなくて「this」に変わった。彼らは、ありありとキリストの霊的実体に触れたのです。
今まで、遠くに「あれ」と呼んでいたものが、「まあ、これ!」と自ら呼べる時にこそ、本当の信仰です。今まで遠くに拝んでいた神様でしたのに、神の御霊に直に触れた時に、「ああ、わが主、わが神」と言う。これが実在に触れる経験なのです。その時に、もう議論は必要でない。自分が直に肌身に触れている、そのものが神なのです。このような直接体験に入るために、すでに信仰に入った人たちが、神の国から抜け出してきたように、予備知識として、たとえをもっていろいろに説くのです。
(※注)ペンテコステ
キリストが十字架にかかられて復活してから50日後に、祈っていた弟子たちに聖霊が注がれた、その日を指す。「聖霊降臨節」ともいう。
たとえの背後の世界を悟る
神学的な考えの人たちのように言葉で神の国の定義がわかったといっても、それは説明であって神の国の中にある居心地とは違います。聖霊に触れる経験と、聖霊についての話とは別です。ヨハネ福音書14章26節にも「聖霊は、あなたがたにすべてのことを教え、わたしが話しておいたことを、ことごとく思い起こさせる」とありますが、私たちが聖霊に満たされる時、聖書がよくわかり、「そうです、アーメン」と言って涙が出てうれしくてたまらない。けれども、聖霊の霊感なくしてどんなに聖書を読んでも、ちっとも面白くない。ここに、キリストがご自分の宗教をたとえでしか語られなかった意味があります。
イエスご自身がたとえでしか語らなかったものを、神学者が偉そうに「神の国はこうである、福音とはこうである」と断定できるのか。むしろそのほうが傲慢ではないかと思う。
キリストは、神の国を理論的にはお説きになりませんでした。野にあっては弟子たちに、「野の百合(ゆり)を見よ」とか「刈り入れ時の麦畑を見よ」と語られました。またスカルの井戸辺では、水を汲みに来たサマリヤの女に、「この水を飲む者はだれでも、また渇くであろう。しかし、わたしにわき出ている霊的な水を汲む者は、その水がその人のうちで泉となり、永遠の生命に至る水が、わき上がるであろう」と言って、すべてたとえをもって語られました。私たちはそのたとえを通してでも、ハッと霊的な実在に触れることが大事なのです。
たとえ話はつまらない、と思う人がいるかもしれません。ところが、話が終わって印象が長く心に残るのは、理論的な話よりもたとえ話です。ですから、イエス様は神の国のことを、いろいろな角度から、たとえにたとえを継いで語りたもうて、飽くことがなかった。聞く人々は、酔うがごとくにイエス・キリストのお話を聞きました。もし、これが神学的な議論だったら、肩が凝ってたまらなかったことでしょう。
柳原白蓮女史のこと
本当の信仰がわかるまでは、神の国はたとえのことです。それが聖霊に触れた瞬間、「神は今ここにおられる」という経験に変わる。その時に説明はいらない。そして、神に触れ、神の雰囲気の中に生きはじめた者には、「私は、なんとありがたい神秘な世界に今、生きているんでしょう」というような生涯が始まります。
大正天皇の伯父さんに当たる、柳原伯爵の娘・柳原白蓮(やなぎわらびゃくれん)は、福岡で炭鉱王といわれた人の妻になり、贅(ぜい)を尽くした赤銅御殿(あかがねごてん)に住んでおりました。柳原白蓮は、大正年間、絶世の美人といわれ、女流歌人としても有名でした。その歌の中に、
われはここに神はいづこにましますや星のまたたき寂しき夜なり
という短歌があります。
彼女は豪華な御殿に住んでいても、心に神はなかった。その時、彼女にとって神は遠い存在でした。4年前、私が東京に行った時、晩年に至った柳原白蓮さんも私たちの集会にやって来られました。そして、「先生、私の目は内障眼(そこひ)で、もう見ることができません。しかし、先生の声を聞くことはできます」と言って、見えない目から熱い涙を流しながら、「今こそ私は、神を目の前に見ることができました」と言って握手しなさった感激を、私は忘れません。それ以来、幕屋の人が白蓮さんのところに行って、『生命の光』を読んでさしあげるのを待ち焦がれておいでになる。私の話を通してでもこの人の心の中に、見えない神のまばゆい光が照りそめたと思う時に、私はうれしかった。これは彼女にとって、「that あれ」が「this これ」になった経験であります。
今ここで神の実在に
このような転換が起こるまでは、たとえで語る以外にありません。信仰において「that」 が「this」に転換するまでは、神様は遠い存在です。
創世記にはイスラエル民族の父祖ヤコブが神と出会った経験が書かれています。ヤコブは父イサクを欺き、兄の祝福を奪ったために兄の怒りを買いました。そして、着の身着のまま父のもとから逃げました。その道中、荒野で日が暮れたので石を枕にして眠りましたら、夢の中に天使が天からのはしごを上り下りするのを見た。神の御声を聞いて目が覚め、「恐るべきかな、この所。ここは神の家、天の門でないか。私は知らなかった」と言ってそこに石を立てて神を拝した、とあります。神を本当には知らなかったヤコブでしたが、眼(まなこ)が開けた時に、荒野に見えた所も天使が上り下りする聖なる場所である、と知りました。
同様にこの集会も、貸し会場の小さなホールです。しかし、私たちの心が開けさえすれば、ここが天です。神は私たちの心の奥にある、内なる至聖所に来たりたもうのであって、外側に、どこかの教会堂や神殿に神の国を見ようとしても、そこに神の国はありません。しかし、どのようにうらぶれて、敗残の身をかこつような状況でありましても、もし私たちの心の中に天地を結ぶ架け橋がかかりはじめたら、そこが聖なる場です。
天を外に、遠くに求めずに、今ここに求めることが大事です。その時にもう、たとえも何もいりません。「ああ、神様」といって直接に神を拝する経験に入ります。この心の転換をしない人には、どんなにたとえにたとえを重ねても同じことです。
どうか、人々が神を外に拝み、客観的に拝もうとしている時に、私たちは内なる至聖所、魂の内奥(ないおう)にて神を拝しとうございます。
(1965年)
本記事は、月刊誌『生命の光』824号 “Light of Life” に掲載されています。