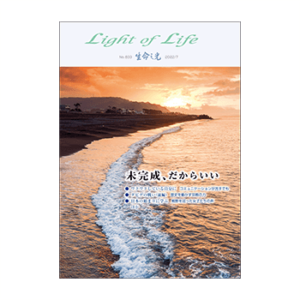聖書講話「ダビデの戦い(前編)」サムエル記上16~17章
―― 歴史を動かす宗教の力 ――
旧約聖書サムエル記の「ダビデとゴリアテ」の物語を読むと、一介の牧童にすぎなかったダビデが、いかにして武器の力によらず強敵に勝利を収めたのか、を教えられます。
私たち一人ひとりも、またわが国も、武力や物量の力に勝る力を与えられたい。この秘密を学ぶために、サムエル記の講話「ダビデの戦い」を、前・後編に分けて掲載いたします。(編集部)
西洋の歴史をひもときますと、キリスト教がヨーロッパの地図を塗り替えてしまうほどに、宗教の力を遺憾なく発揮したことがよくわかります。
その基となられたイエス・キリストは偉大だったでしょう。しかし、わずか3年の伝道の後に、十字架にかかって亡くなられました。またその後を継いで信徒たちを指導したのは、ガリラヤの無学な漁師ペテロやヨハネたちでありまして、人々は彼らに何ができるだろうかと思いました。世の人は、政治家が政治力で、学者や思想家が知識によって、また将軍が軍隊の力をもって、歴史に影響を与えることができると思っております。
ところが、神学者でも思想家でもないナザレの村の一大工であったイエス、その弟子のペテロたちによって打ち立てられた宗教が、現在に至るまで世界の歴史や思想、また諸国の文明に、多大な感化、影響を与えております。何がこのようなつまらない無学なただ人を通して働き、歴史を動かしたのでしょうか。
この秘密を一言で言うならば、神の霊の力、超自然的なエネルギーが働いたからであります。それを受けて、普通の人間にはない新しい生命が、心の底からわき上がったからです。この、神の霊の泉がわいてくる経験が大事です。これを得るために私たちは祈るのです。これによって神霊の力の法則を学ぶのです。
神の霊を注がれるという経験
それについて、旧約聖書のサムエル記に書かれている、神の霊を注がれたダビデという少年の物語を通してお話ししたいと思います。この少年こそ、後にイスラエルを治めて宗教的黄金時代を築いたダビデ王であります。
さて、紀元前10世紀ごろ、サウル王が最初の王として立てられてイスラエルを治めていた時、神は預言者サムエルに告げられました、「わたしはサウルを王としたけれども、彼は傲慢(ごうまん)になってわたしの心を行なわなくなった。それゆえベツレヘムへ行って、サウルに替えてエッサイの子を選び、これに油を注げ」と。
神に言われたとおりにサムエルが出かけると、そこにはエッサイの7人の息子がおりました。ところが、サムエルが彼らを見回しましても、心に適う者がおりません。それで、「これで全員か」と聞くと、父親のエッサイは、「もう一人おりますが、野で羊を飼うよりほかに役に立たない、つまらない子供です」と答えました。
「いや、その子を連れてこい」と言うので、サムエルの前に連れられてきたのが、末っ子のダビデでありました。
彼(ダビデ)は血色のよい、目のきれいな、姿の美しい人であった。主は言われた、「立ってこれに油をそそげ。これがその人である」。サムエルは油の角をとって、その兄弟たちの中で、彼に油をそそいだ。この日からのち、主の霊は、はげしくダビデの上に臨んだ。
サムエル記上16章12~13節
ここに書かれている「油注ぎ(注1)」とは一つの儀式ですが、預言者サムエルはそれに託してダビデを聖別し、神の霊が激しく臨むように執り成したのであります。
人間は、自分たちを単なる哺乳動物の一種にすぎないと思っております。しかし、神の目からご覧になったら、はるかに尊い存在として映っているのです。なぜなら人間は他の動物と違って、神の世界に流れている霊的生命、神の霊を受けることができるからです。ここに宗教の課題があり、わけてもキリスト教はそれを主張するのであります。
「キリスト」とは何か。それはギリシア語で「油注がれた者」という意味です。それでクリスチャンとは「キリストのように油注がれた者」、すなわち神の霊が注がれた者をいいます。まず御霊を注がれる経験をしなければ、キリストの弟子であるクリスチャンではありません。

では、人間に神の霊が臨みだすと、どうなるか。サムエルがダビデに油を注いだ後に、どういうことが起きてきたか。それがサムエル記に書かれております。
サウル王が信仰を失って悪霊に苦しんでいた時に、こう王に告げる者がいました。
「わたしはベツレヘムびとエッサイの子を見ましたが、琴がじょうずで、勇気もあり、いくさびとで、弁舌にひいで、姿の美しい人です。また主が彼と共におられます」
サムエル記上16章18節
ダビデは、父親からもつまらないといって軽んじられ、のけ者にされていましたが、ひとたび神の霊が臨んだら、彼にコンバージョン(回心)が起きました。そして、サウル王が悪霊に苦しめられ病んでいる時に、ダビデが呼ばれて竪琴(たてごと)を奏でると、音色だけで王の病をいやすほどの不思議な能力(ちから)が伴いはじめました。
また、ただの羊飼いの少年ではなく、彼に任されている羊を襲ってくる熊や獅子を素手で投げ打つことができるような、勇気ある戦人(いくさびと)となりました。それに、詩人のように、預言者のように弁舌にも秀でた人間になった。彼の作った詩篇23篇や51篇などは優れた信仰詩で、2900年後の現代に至るまで多くの人々に愛され、うたわれております。
私たちは、神の霊を注がれることが何であるかを知らねばなりません。神の霊は、このように人格をガラッと変える力をもっています。これが福音です。教育ではできません。
同様に、こういう力が来なかったならば、貧しいガリラヤの漁師でしかなかったイエスの弟子たちが、世界の歴史に感化を与えたりするものですか! 私たちは、この信仰の奥義を握らねばなりません。
(注1)油注ぎ
旧約聖書の時代、祭司や王などの任命に際して、頭上に油を注いだ。油は神の霊を象徴するもので、これによってその人を聖別するためであった。
「蒙を以て正を養う」
ダビデのように神の霊が注がれるということは出発点であって、「ああよかった、もうこれで満足だ」というところに止(とど)まっていてはだめです。皆さんは「集会で祈って聖霊を注がれたからうれしい」と言いますが、それが目的ではありません。聖霊が臨んだのならば、そこから次に信仰の完成を目指さなければならない。生命は必ず伸びるものだからです。
それについて思うことがあります。2月11日は紀元節、今でいう「建国記念の日」です。その日が近づくと、それを記念するのがいいとか悪いとかいって、世間では議論があります。しかし私は、神武天皇というお方を尊敬しております。神武天皇がおられたからこそ日本は統一されたのです。そして、日本を一つに仕上げられた天皇が、綿々として今に至るまで国家的に元首として存在しておられます。これは間違いのない事実であります。
『日本書紀』に記されておりますが、神武天皇のご一行が九州の日向(ひゅうが)から出発して、数年かかって大阪の浪速(なにわ)まで来られました。そして大和に入ろうと、生駒山の暗峠(くらがりとうげ)にさしかかりました。その峠で地元の有力豪族・長髓彦(ながすねひこ)の激しい攻撃を受けました。
すると神武天皇は、「自分は日の神の子孫にして、日に向かって敵をうつのは、天道に逆らっている。今は退いて自分の弱きを示して、天つ神、国つ神をまつろう」と言って、草香津(くさかのつ)まで退きました。そこでご自分の盾を捨てて雄叫びして祈られ、天の助けを得て危機を切り抜けられました。
その後、神武天皇ご一行は紀伊半島を迂回して熊野に上陸し、幾度も天つ神に祈りつつ、武力でなく天の御稜威(みいつ)によって敵に勝利し、大和入りされました。
ついに奈良の橿原(かしはら)に都を定められた時に、「わが皇祖(みおや)の霊(みたま)は天(あめ)よりくだりみそなわして、わが身を光(て)らし助けたまえり」と言って、まず天つ神をまつっておられます。
神武天皇は、このようにめでたく大和に入ることができたのは、自分たちが蒙(もう)を以(もっ)て正を養ったからであるといって、「蒙を以て正を養う」という有名な言葉を言われました。
これは『易経(えききょう)』に出てくる言葉ですが、「蒙」という字は、童蒙(どうもう)という言葉があるように、子供のような未開な状態をいいます。「正」というのは完成です。この言葉はいろいろな解釈ができますが、未開の状態であればこそ完成を目指して努め、自分を養ってゆくことができる、という意味があります。このように神武天皇は、完成するまでは九州の未開地、蒙昧(もうまい)な地におられ、蒙を以て正を養っておられたというのです。
人間は一足飛びに大人になったり、完成するものではありません。すべて未開発の子供のような蒙の状態を経て、だんだん完成に向かって養われてゆくのです。「もう自分はでき上がった」という者には成長がありません。でき上がらない者が尊いんです。
ですから「私はもう信仰がわかっている」というでき上がったクリスチャンを、私は好みません。私たちにとって未開発であることが尊いんです。
来たるべき時代への備えとして
ダビデは神に愛され、預言者サムエルによって油注ぎを受けました。けれども、ダビデはそれが何のためであるか、初めはわかりませんでした。しかし、それがものを言う日が近づいてきました。不思議な能力(ちから)が彼に伴いはじめ、いよいよイスラエルに国難がやって来た時に役立つのであります。そして、周りから役に立たない少年と思われていたダビデが、神霊の力を、彼の本領を発揮することとなります。
大石内蔵助(おおいし くらのすけ)といえば、赤穂浪士(あこうろうし)四十七士の討ち入り(注2)の中心人物として有名です。彼は、浅野家の家老でしたが、「大石の昼行灯(ひるあんどん)」と言われて、昼間に灯(あかり)をつけても役に立たない行灯のように、馬鹿なのか利口なのかわからない人間だと思われていました。もし、主君の浅野内匠頭(あさの たくみのかみ)が刃傷(にんじょう)の責めを負って切腹に処せられるという事件が起こらなかったならば、赤穂の片隅で一生を終わっていたかもしれません。小藩にこんな素晴らしい家老がいたということは、浅野家に危機が及んだからこそわかったのです。彼は隠れた本領を発揮し、人々はその偉大さを知りました。
時代が行き詰まってまいりますと、神は必ずそれを乗り越えてゆくための備えを、人々の知らないところでなしたまいます。イスラエルの歴史において、神は一人の少年ダビデを選び、油注ぎをされ、民族の危機に対する備えとなしたまいました。
ダビデと同様に私たちも、人は知らずともよい、また人は罵(ののし)ってもよい。少数の、御霊の油を注がれた民である、そして、次の日本の歴史を担う者たちであるという自覚をもつ必要があります。そうでないならば、せっかく私たちの一群に不思議な御霊注ぎが始まっていることが、ただそれだけで終わってしまいます。
(注2)赤穂浪士討ち入り
江戸時代の元禄年間に起きた事件。江戸城中にて吉良上野介(きら こうずけのすけ)に斬りつけた赤穂藩主・浅野内匠頭は切腹を命ぜられ、赤穂藩も改易。浪士となった藩士たちは2年後、吉良邸に討ち入り、主君の仇を取る。この事件は「忠臣蔵」と呼ばれ、歌舞伎や芝居の題材として好まれた。また、その後の武士道に大きな影響を与えた。
ペリシテ人との戦い始まる
さて、ダビデが油注がれてしばらくたった時、長い間イスラエルを苦しめていたペリシテ人が、戦おうとして軍を集め、イスラエルに属するエペス・ダミムという所に陣取りました。ペリシテ人はもともと地中海の海洋民族で、当時は先進民族として優れた文明をもっていました。
サウルとイスラエルの人々は集まってエラの谷に陣取り、ペリシテびとに対して戦列をしいた。ペリシテびとは向こうの山の上に立ち、イスラエルはこちらの山の上に立った。その間に谷があった。時に、ペリシテびとの陣から、ガテのゴリアテという名の、戦いをいどむ者が出てきた。
サムエル記上17章2~4節
エラの谷は、ダビデが生まれたベツレヘムの西の方にある谷間で、そこで双方の数万の軍隊が集結して対陣し、膠着(こうちゃく)状態になって打開策を求め、焦っておりました。
ついにペリシテ人の中から、見上げるような大男のゴリアテという百戦錬磨の勇士が、一騎打ちを挑んできました。頭には青銅の冑(かぶと)、身にうろことじの鎧(よろい)、足には青銅のすね当てを着け、肩には重い穂のついた青銅の投げやりを背負っている。
この歴戦の勇士が、「1対1の勝負で、負けたほうが勝ったほうの家来、奴隷になって仕えなければならない」と言いました。しかし、ゴリアテに対してとても勝ちめがないと思って、サウル王はじめイスラエルの陣営からはだれも応ずる者がおりませんでした。
この戦いにダビデの兄たちも参加しておりました。父親のエッサイは、「兄たちのようすを見に行ってこい」と言って、ダビデを陣中見舞いに送り出しました。ダビデがエラの谷に着いてみると、ちょうどゴリアテが出てきて大変な騒ぎになっていました。
サウル王は真っ青になって、「戦う者はいないのか。もしゴリアテに勝ったならば、多くの財産を与え、自分の娘を嫁にやろう。そして、その者の家は税金を納めなくてよろしい」と言いました。一躍、王族に取り立てるというのですが、それでも戦おうという兵士はいません。それを見てダビデは怒って、傍らに立つ人々に言いました。
「このペリシテびとを殺し、イスラエルの恥をすすぐ人には、どうされるのですか。この割礼なきペリシテびとは何者なので、生ける神の軍をいどむのか」
サムエル記上17章26節
「割礼なき」というのは「信仰のない」という意味です。ダビデは、「味方からだれも一騎打ちに出る者がいないとは、一体どういうことだ」といぶかしく思った。「イスラエル」とは「神の民」の別名です。神の民がこんなに侮られ、馬鹿にされてよいものか、これではたまらない! というのが彼の言い分でした。
同様に、私たちが神の世界に目覚めるためには、まず「現在のように宗教が無力ではたまらない」と言いださなければだめだということです。これが大事です。「宗教を信じている、またクリスチャンであると言いながら、なんと無力で、ふがいないことだろうか。こんなに罵(ののし)られて平気でいるとはたまりません」と、こんなことを私が言うと、必ず物議を醸します。しかし、だれかが言わなければ目覚めるということはないんです。
ダビデの信仰の秘密
兄のエリアブは、ダビデがそう言っているのを聞いて、羊を飼うしか能のないやつが何を言うか。3メートル近い歴戦の勇士が、甲冑(かっちゅう)に身を固め大きなやりで挑んでくる。だれが彼に立ち向かうことなどできるものか、と怒りました。これは、兄たちの常識です。
ところが、ダビデの言ったことがサウル王に聞こえました。それで王の前に引き出されました。するとダビデは、「王様、ご心配いりません。私があのゴリアテと戦いましょう」と、事もなげに言います。サウル王はビックリして、「おまえはまだ年少ではないか。無謀すぎる。相手は若い時からの軍人で、負けたことのない者だ」と言いましたが、しかしダビデはなおも、私が行きますと答えました。
大事なのは、ここです。王様の目から見ても勝つ見込みがない少年ダビデ。けれども、若いからといって侮られる必要はありません。若ければこそ、何をやるかわかりません。これは年齢の若さだけでありません。与えられた神の新しい生命が偉大なことをなします。
どうしてここで、ダビデは「戦います」と言えたのか。それは、「かつて羊が熊に襲われた時に、私は熊を倒し、獅子がやって来た時には、そのひげをつかまえてなぎ倒しました。何が秘密か。それは、神が私と共におられるからです」と言いました。自分の腕力で倒したとは思っていません。同様に、神の霊力が自分に働いているから、今度も勝利できる。自分こそ戦う資格があると信じて、ゴリアテとの戦いに向かいます。
自分は神の人サムエルから神の霊が注がれるように執り成され、油注ぎを受けた者である、という自覚があったからです。これは、私たちが共通にもたなければならない自覚です。神の霊が共にあるがゆえに、勇気を出して困難に赴くことができます。(次回に続く)
(1965年)
本記事は、月刊誌『生命の光』833号 “Light of Life” に掲載されています。