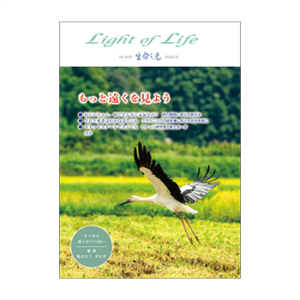英詩講話「されど勇者は行かねばならぬ」―ロバート・ブラウニング作「PROSPICE」―
人生最大の問題は、死の突破にある。死を恐れ、忘れて生きようとするのか、それとも死を恐れず、死に立ち向かいつつ生きるのか。19世紀の英国詩人ロバート・ブラウニング作の「PROSPICE プロスピシー 展望せよ」は、年配の人にはもちろん、若い人にも語りかけます。
今回は、手島郁郎が一人の弟子を哀悼しつつ語った、ブラウニングの詩の講話を掲載いたします。(編集部)
PROSPICE
by Robert Browning
プロスピシー
ロバート・ブラウニング作
Fear death?─to feel the fog in my throat,
The mist in my face,
When the snows begin, and the blasts denote
I am nearing the place,
恐るるや 死を ―― 喉(のど)には濛気(もや)を
わが顔には 狭霧(さぎり)を感ずるを
雪降りはじめ 嵐の徴(きざし)ある時
私は その場所に 近づいている
The power of the night, the press of the storm,
The post of the foe;
Where he stands, the Arch Fear in a visible form,
Yet the strong man must go:
夜陰の力 暴風雨激しく
敵のたむろする所 そこに立つは
恐怖の首魁(しゅかい)のありありとした姿
されど勇者(強者)は行かねばならぬ
For the journey is done and the summit attained,
And the barriers fall,
Though a battle’s to fight ere the guerdon be gained,
The reward of it all.
I was ever a fighter, so ─one fight more,
The best and the last!
旅は終わり 絶頂を極む
また城壁も崩れ落つ
けれども戦うべき一戦あり
褒美を得るまで その報いすべてを得るまでに
私は常に戦士(ファイター)であった さればさらに一戦
最善最後の一戦を!
I would hate that death bandaged my eyes, and forbore,
And bade me creep past.
No! let me taste the whole of it, fare like my peers
The heroes of old,
Bear the brunt, in a minute pay glad life’s arrears
Of pain, darkness and cold.
私は厭(いと)う 死がわが目を覆い
大目に見て 腹ばいて通過せしむることを
否! 死の凡(すべ)てを私に味わわしめよ
わが先輩たち 古(いにしえ)の英雄のごとく進みゆき
矢面に立ち 一瞬間にして
苦しい年貢 ― 暗黒と冷酷 ― を喜んで支払おう
For sudden the worst turns the best to the brave,
The black minute’s at end,
And the elements’ rage, the fiend-voices that rave,
Shall dwindle, shall blend,
Shall change, shall become first a peace out of pain,
Then a light, then thy breast,
O thou soul of my soul! I shall clasp thee again,
And with God be the rest!
そは 勇者には忽(たちま)ち最悪が最善に変ず
暗黒の瞬間 終わり
風雨の怒り わめく鬼魔(きま)の声も
衰え 混ざり 変わりゆきて
まず 苦痛より出ずる平和となり
次に一つの光現れ 続いて御身の胸が……
おお、なんじわが魂の魂よ! われ再びなんじを抱きしめん
その余のことは 神ながらのままに!
今日、皆さんとお読みする「PROSPICE プロスピシー(展望せよ)」という詩は、ブラウニングの妻であったエリザベスが死んだ後、すぐに書かれた作品です。妻に先だたれ、彼は大変な悲しみに陥りました。今まで苦楽を共にした妻、その死ぬ間際の苦しげで気の毒なありさま。ひどい痛みとたたかって死んでいった姿を見れば、だれもが死を恐れるでしょう。しかし、彼はこの詩を書くことによって、自分がいちばん恐れていた「死」を見事に解決したのです。
PROSPICE(プロスピシー)というのはラテン語です。英語ならば、「Look ahead.(ルック アヘッド) 前を見よ」という命令形の言葉です。「展望せよ」とか「前を見よ」と訳せばいいですね。
妻のエリザベス・バレットは、もともと富裕な家のお嬢さんでした。夫のロバートより6歳年上の彼女は、結婚前は肺結核で、そのうえ脊髄を病んでおりましたが、非常に才気煥発(さいきかんぱつ)な人で、若いころから女流詩人として、イギリスではいちばん世に聞こえた人でした。ブラウニングに出会ってお互い想い合うようになりましたが、親に反対され、幾年も結婚できませんでした。
当時のブラウニングは、まだだれからも認められていない無名の詩人でした。彼の詩は非常に難しいのです。英語も難しいが、思想も高邁(こうまい)で意味がよくわからない。しかしそれだけに、読めば読むほど味が出てきます。
彼が重んじたのは、聖書の思想、ヘブライズム(※注)でした。老年期を迎えて「最善はこれからだ。われらの時は神の聖手の中にあり」とうたった「ラビ・ベン・エズラ」という詩を見てもわかりますように、神様に従って現実の人生を戦い、冒険しながら人間の内なる霊魂は陶冶(とうや)されてゆくことを、高らかにうたっております。
エリザベスは彼の詩人としての価値を認めて励ましつづけましたが、世の中には受け入れられませんでした。しかし彼女の死後、だんだんとブラウニングの詩の真価が一般に認められるようになって、どのくらい多くの人に感化を与えたかわかりません。
この詩は、ブラウニングが妻を失った悲しみのどん底から詠い上げた、大きな覚悟を示しています。詩の主人公は、妻であり、ブラウニング自身でもあります。
(注1)ヘブライズム
旧約聖書を生み出した古代のヘブライ人(ユダヤ人)の思想、信仰を指す。同様に西洋思想に影響したヘレニズムが、人間中心的、観念的であるのに対し、ヘブライズムは神とその啓示を中心とした現実主義的なあり方を重んじる。
死を恐れるか?
恐るるや 死を ―― 喉には濛気(もや)を
わが顔には 狭霧(さぎり)を感ずるを
雪降りはじめ 嵐の徴(きざし)ある時
私は その場所に 近づいている
Fear death?─to feel the fog in my throat,
The mist in my face,
When the snows begin, and the blasts denote
I am nearing the place,
この「Fear death?(フィアー デス)」は、本来ならば「Do I fear death?(ドゥー アイ フィアー デス) 私は死を恐れるのか?」です。「喉には濛気を感ずる」とありますが、妻のエリザベスは肺の病気でしたので、靄(もや)が喉に詰まったようになりました。呼吸困難になって死ぬ時の、断末魔の苦しみほどひどいものはない。さらに、顔に霧がかかったように目の前がぼんやりしてくる。死ぬ前は目は開いていても、意識が遠のいてだんだん見えなくなってゆきます。
そして、雪が降りはじめる。このような天候の描写で、死が近づいていることを表現しているのです。死ぬ時には手足が冷たくなりますね。また、「the blasts denote(ザ ブラスツ ディノート) 嵐が徴(きざ)す」とは、耳鳴りがすることです。臨終に際してガンガン耳鳴りがしてくる。そうして 「I am nearing the place,(アイ アム ニアリング ザ プレイス)」私はその場所、死に近づいているのだ、というわけです。
復活の生命があれば
夜陰の力 暴風雨激しく
敵のたむろする所 そこに立つは
恐怖の首魁(しゅかい)のありありとした姿
されど勇者(強者)は行かねばならぬ
The power of the night, the press of the storm,
The post of the foe;
Where he stands, the Arch Fear in a visible form,
Yet the strong man must go:
敵の立つ所、そこは真っ暗なやみの力が働く場所であり、嵐が吠え猛っている。死の関門というのは、聖書的に言うならば万人の敵である「死」がたむろしている場所。そこに近づきつつあるという。ここに恐怖の頭目が「in a visible form,(イン ア ヴィジブル フォーム)ありありと目に見える姿で」立っている。サタンなどというものは目に見えない存在ですが、それが見える形で立っているような恐ろしい所にはだれだって行きたくはない。だれでも死は回避したいものです。
しかし、「Yet the strong man must go:(イェット ザ ストロング マン マスト ゴー) されど勇者(強者)は行かねばならぬ」でして、自分は強い人間である、というんですね。私は弱々しいクリスチャンではない、強いクリスチャンであった。だから死というものを回避したり、恐れたりすべきではない、と。
だれでも死は嫌です。しかし、嫌だ嫌だと言っている間は、いつまでも力が出ません。私たちは、いちばん恐ろしいものと立ち向かおうとするときに、ほんとうに勇気が出てきます。なぜならば、使徒パウロが「死は勝利(かち)に呑(の)まれたり」(コリント人への第一の手紙15章)と言ったけれども、イエス・キリストの有しておられた復活の生命、勝利の生命は、死の力をも呑み干してしまうのだから、キリストに信頼しまつる私たちは死を恐れてはなりません。
「Yet the strong man must go:(イェット ザ ストロング マン マスト ゴー)」、死ほど怖いものはない。しかし、その死を踏んづける人間になりましたら、ほんとうに強いです。何でもできます。
新保恒男さんの生きぶり
1週間前、高知で伝道していた新保恒男君が自動車事故に遭い、46歳で亡くなりました。自動車で高松に行く途中、四国の難所であり、素晴らしい渓谷沿いに断崖絶壁の坂道がうねっている大歩危小歩危(おおぼけこぼけ)での事故でした。新保君は肺病上がりの弱い体でしたが、仙台や飯塚(いいづか)、大分など、それまで幕屋のない所で伝道して幕屋を立ち上げてきなさった。だがこの3年間、彼は高知にいて「このままではいけない。高知はだれかに任せて、自分はもう一度、無から始めたい」と思った。それで、「今、四国の玄関口である高松にまだ幕屋がない。まず、ぼくがそこに移住して開拓伝道をするから、助けてほしい」と言って、近隣の伝道者諸君に声をかけて、共に出かけようとしていた矢先でした。
新保君は小さい時、両親に死に別れ、小学校を出ただけでしたけれども、よく聖書を原文から勉強していました。大学出の人よりその聖書ギリシア語の読解は確実でした。そして何よりも、温かく、飾らない信仰をもって生き、人を慰めておりました。肺病で肋骨を取っているので、外見は風采の上がらぬ人です。また、もの静かな人でした。しかし、病弱で畳の上で死ぬはずだった彼が、使命を抱いて伝道に行く途上で殉職したのです。
人に号令をかけるようなことをしない人が、どうして先輩の伝道者にまで号令をかけ、高松の開拓をやろう、と言うようになったか。私はその秘密を知りたいと思いました。
葬儀に参りますと、棺(ひつぎ)の上に彼の聖書が置いてあった。彼が死ぬまで持っていた聖書でした。そこにたった一つ、この「PROSPICE(プロスピシー)」の詩がはさんでありました。私はそれを見た時に、「ああ、ここに新保君の秘密があった。彼は死を覚悟しておった」と知りました。
この詩は、今から16~17年前でしょうか、彼が熊本の聖書塾で学んでおりましたころ、私が講義したものです。それを新保君は大事にして、死ぬまでこれを持って、死と対決した。死と対決する者はこうも強くあるのか。だから弱いはずの新保君が、そのような壮烈な最期を飾ることができたのか。
私は彼に言ったことがあります、「君は、肺病だからといって、いつ死ぬかと恐れてばかりいたならば何もできない。細く長く生きようと思うな。太く短く生きるんだ。人間、一度死ぬことを決心しさえすれば、ほんとうに強く生きられる。死を覚悟せよ」と。
人間の最大の問題は、死ということです。このことを解決しないならば、人生はいくら成功に見えても失敗です。しかしながら、ひとたび人生の最後、墓のかなたにまで行くだけの力を蓄えたならば、それこそ私たちは人生の勝利者ということができるでしょう。
最善最後の戦いを
旅は終わり 絶頂を極む
また城壁も崩れ落つ
けれども戦うべき一戦あり
褒美を得るまで その報いすべてを得るまでに
私は常に戦士(ファイター)であった さればさらに一戦
最善最後の一戦を!
For the journey is done and the summit attained,
And the barriers fall,
Though a battle’s to fight ere the guerdon be gained,
The reward of it all.
I was ever a fighter, so ─one fight more,
The best and the last!
「journey(ジャーニー) 旅」とは、ここでは人生のことです。人生の旅は終わり、絶頂までたどり着けた。「barriers(バリアーズ) 防壁」というのは生と死とを隔てている壁のことです。来世と現世の壁は、今まさに落ちようとする。けれども戦うべき一戦がある、この褒美を受けるための。
褒美というのは、一生のすべてに対する報い、ということです。最後の戦いをどう戦うかによって、自分の魂の真価といいますか、来世での褒美も違ってくるということです。
ここに「summit(サミット) 絶頂」とありますが、「青年時代は華やかでよい、壮年時代は活躍期でよい」というこの時代の思想に対して、ブラウニングは「老年こそ人生の絶頂期である」と言う。40、50は、はなたれ小僧であって、60を過ぎなければ人生の豊かさ、うましさというものはわかるものではない。こういう思想に立っております。
だれでも普通は、年を取ることを嫌います。私の同輩の連中でも、定年退職してしまうと昔のような威勢のよさがありません。たまに集まると、「やあ、お互い年を取ったなあ」と言って、ため息をついています。私と全く違います。霊魂が目覚めていなければ、年を取りたくないのは当たり前です。死ねば肉体は何も残らないからです。
年を取れば肉体は衰える。けれども霊魂は永遠の生命を求めて日々に成長し、老いることを知りません。死を間近にして霊魂は円熟してきます。人生でいちばん素晴らしい時はいつか? 華やかな青年時代ではない、晩年の老年期です。老年を活かすのが信仰です。
さらに続けております、「私はいつも戦士(ファイター)であった。だからさらに一戦しなければいけない。しかもその一戦は、自分にとって最善にして最後の戦いである」と。死というものは、人生最後の、そして最大の戦いです。この死によく勝ちうるかどうかによって、その人の価値というか、次に行く天国での位も決まるのだ、という意味でしょう。
死のすべてを味わって
私は厭(いと)う 死がわが目を覆い
大目に見て 腹ばいて通過せしむることを
否! 死の凡(すべ)てを私に味わわしめよ
わが先輩たち 古(いにしえ)の英雄のごとく進みゆき
矢面に立ち 一瞬間にして
苦しい年貢 ― 暗黒と冷酷 ― を喜んで支払おう
I would hate that death bandaged my eyes, and forbore,
And bade me creep past.
No! let me taste the whole of it, fare like my peers
The heroes of old,
Bear the brunt, in a minute pay glad life’s arrears
Of pain, darkness and cold.
私は、死が私の目に包帯してくれて安楽死する、などということは嫌だ。腹ばってゆくことをcreep(クリープ)といいますが、「こそこそ忍び寄る」といった意味にも使えます。死が「こいつは弱虫だから、なるべく安楽死させてやろう。目隠しして寛大にしてやって、あまり無理はさせんでいい」と言わんばかりに、死の前をこそこそ腹ばって通過することを許す。しかし、「否!(ノー) 死の凡てを私に味わわしめよ」とブラウニングは叫んでいます。
日露戦争のころ、日本の特務機関の2人の工作員がロシア軍に捕らえられて銃殺されました。そのうちの1人、沖禎介(おきていすけ)は「わしは目隠しなんか要らん。自分が死ぬさまをこの眼で見て死にたい」と言って、目隠しを断り、じっと相手を睨(にら)みつけたまま撃たれて死んでゆきました。そのように、目隠しされずに我慢することを望む、というわけです。
また、使徒パウロのように、「死よ、おまえの勝利は、どこにあるのか。死よ、おまえのとげは、どこにあるのか」(コリント人への第一の手紙15章)と言って、死に対して堂々と四つに組んで倒れてゆくというのです。えらい度胸です。これが真の聖書の信仰ですね。
「死の凡てを私に味わわしめよ わが先輩たち(peers ピアーズ)のごとく進みゆき」と言う。このpeer(ピアー)という言葉は、地位や才能、考えなどが自分と同列である人を指します。ここでは、同窓の先輩と言えばいいでしょうか。古の英雄、すなわち私の先輩たちが、死をものともせず殉教していったように、ということです。
イエス・キリストは十字架にかかられる前、痛みを和らげるためローマ兵が苦みを混ぜたぶどう酒を飲ませようとしましたが、お飲みになりませんでした。現代でも、死の間際に麻薬を打って苦痛を和らげます。それならば楽でしょう。しかし、キリストは「死の最後の一滴(ひとしずく)までわたしに味わわしめよ」と言わんばかりに、それを拒絶なさったのです。
昔の英雄のように死の矢面に立って、人生の未払い金――最後まで残されて滞った義務arrears(アリアーズ)――苦しい暗黒と冷酷、つまり死という未払い金を、私に支払わせよ。死の最後は苦しいし、真っ暗で冷たい。けれども、これを一瞬にして喜んで支払おう、というのです。どうして「一瞬」かというと、苦しいのは死ぬ時の一瞬であって、やがて喜びと平安の世界に変わってゆくからです。
勝利した者の平安
そは 勇者には忽(たちま)ち最悪が最善に変ず
暗黒の瞬間 終わり
風雨の怒り わめく鬼魔(きま)の声も
衰え 混ざり 変わりゆきて
まず 苦痛より出ずる平和となり
次に一つの光現れ 続いて御身の胸が……
おお、なんじわが魂の魂よ! われ再びなんじを抱きしめん
その余のことは 神ながらのままに!
For sudden the worst turns the best to the brave,
The black minute’s at end,
And the elements’ rage, the fiend-voices that rave,
Shall dwindle, shall blend,
Shall change, shall become first a peace out of pain,
Then a light, then thy breast,
O thou soul of my soul! I shall clasp thee again,
And with God be the rest!
「突然に、勇者にとっては最悪が最善に変わる」、いい言葉ですね。勇者、死を恐れない者にとっては、死という最悪も最善に変わるからです。夜陰の力が支配する暗黒の瞬間が終わる。そして、冒頭に出てきたような暴風雨の怒りも、わめくような悪鬼の声も、だんだん衰えて小さくなってゆく。死の暴力とでもいうのでしょうか、ブラウニングの妻は大変苦しんで死んだのでしょう。しかし、やがて死んでしまうと平和な顔に変わってゆく。この「peace(ピース) 平和」は単なる平和でなくて、苦しみのどん底から現れた平和ですね。仏教でいうならば涅槃(ねはん 世の苦しみや煩悩を離れた安らぎの境地)でしょう。
エリザベスは、イタリアのフィレンツェで夫と滞在していた時に肺病が再発しましたが、医者を呼びに行かせる間に、夫の胸に抱きしめられながら息を引き取ってゆきました。
その姿を見ていたからでしょう、ブラウニングは自分が死ぬ時も、妻のように断末魔の苦しみに耐えるが、やがて平和が内によみがえって安らかになる。次には光が射しそめ、続いてあなたの胸が――「thy breast(ザイ ブレスト) なんじの胸」は、妻のエリザベスのことです。「私に抱かれて死んでいったエリザベスよ、わが魂の魂、わが骨の骨よ、私が死ぬ時にもう一度、あなたの胸を抱きしめたい」と。
「with God be the rest!(ウィズ ゴッド ビー ザ レスト) 後のことは、みな神と共に!」、天国に行ってからのことは、すべて神様の思(おぼ)し召しのままに、ということですね。神様と共にありさえすれば、すべてが備えられる。他のことは何も案じることはない。神様と共にあることが最善なのです。
こう言ってブラウニングは妻の死を悼み、また新しい決心を述べたのです。死に真っ向から挑戦して、ほんとうに平和な眠りに就いた妻。このような人の死を通して、彼は大きな霊感を覚えたのです。そして、「私も妻に倣って、そういう死に方をしよう」と思ってからのブラウニングは、実に素晴らしい作品を次々と生み出してゆきました。
この詩を抱いて死んでいった新保恒男君、君は死を恐れずに、「さあ、皆で行こう」と言って伝道の門出に立った。そして志半ばにして指揮官自ら自爆したのです。畳の上で死ぬはずだった病弱な人が、です。私はこの詩を彼に贈るとともに、その壮烈な死をほんとうに称えます。かつて私が教えたこの詩を、彼が聖書にはさんで死んでいったことを思うと、愛(いと)おしくてなりません。
聖書の字句を読むこともよい。しかし、その聖書の言葉をほんとうに生き、死に勝利した人たちの生涯を顧みることは、もっと大事です。それによって、また次々と偉大な魂が生まれてまいります。
(1969年)
本記事は、月刊誌『生命の光』835月号 “Light of Life” に掲載されています。