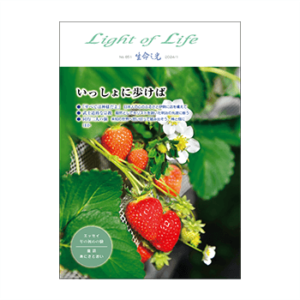信仰講話「同行二人の旅」
わたしは山に向かって目を上げる。
詩篇121篇1~5節 私訳
わたしの助けはどこから来るだろうか。
わたしの助けは主、エホバから来る。
天と地とを造られた主から来る。
あなたの足の揺らぐことなきよう、
あなたを見守る者は、まどろむことを許されない。
見よ、イスラエルを守る者は、まどろみ、眠ることもない。
主、エホバこそ、あなたを守る者。
主こそ、あなたの右の手をおおう陰だ。
これは有名な詩篇として、多くの人々に親しまれていますが、昔、リビングストン(注1)は、アフリカの恐ろしい奥地へ伝道に出かけるに当たって、この詩を読んで出発したそうです。
(注1)デビッド・リビングストン(1813~1873年)
スコットランドの探検家、宣教師。ヨーロッパ人で初めて、当時「暗黒大陸」と呼ばれていたアフリカ大陸を横断した。
これは「都もうで」、すなわちエルサレムの都に向かう巡礼の歌ですが、果てしない砂漠の地を旅しながら、行く手をはばむようにそそり立つ険しい山々を見て、巡礼者たちは、「どうしてこの弱い足で、あの山まで行けるだろうか」と無力な自分に泣きたくなったのです。伏し目がちにうつむいて、絶望のため息をもらしている巡礼者の一群。左を向いても右を向いても、どこからも風一つなく、風も死んでしまって、焼けつくような炎熱の中を、太陽がギラギラと砂漠を燃やして、息苦しい旅を続けているキャラバンの一団を、ご想像ください。
こんな砂漠を旅することは、恐ろしいことです。気がゆるんだら、たちまち死んでしまいます。”天は燃ゆ山もえ地もえ空気もゆ心を燃やせ巡礼の友”と、私も若い人々を励ましたことがありますが、砂漠を旅しつつ、もし水に渇くと死にます。いくらお金があっても、お金を食べて渇きが止まるものでもなく、渇き死にします。もう残るところ自分の気力だけでして、ただ精神力を燃やして歩かねばなりません。
念力のゆるめば死ぬる大暑かな
村上鬼城(むらかみ きじょう)
所詮、人生は旅です。「人間は、魂の故郷(ふるさと)を求めて地上では永遠の旅人、寄寓者(やどりびと)として歩かねばならぬ」とヘブル人への手紙11章にあります。人間は天涯の孤客、どこかに救いが、希望がないかと、周囲を見渡したくなります。松尾芭蕉も詠いました、
西東あはれさおなじ秋の風
此道(このみち)や行人(ゆくひと)なしに秋の暮
キェルケゴール(注2)は、「絶望とは、死に至る病である」と申しましたが、砂漠に旅して、絶望したら死にます。
信ずべくもない時にも、望み、信じつづけるのが聖書の信仰です。原文のヘブライ語では「エサー エイナイ エル ヘハリーム〈私は上げる 私の両眼を 山々に向かって〉」と詠いだして、今まで沈んだ気持ちで下を向いていた人が、急に眉(まゆ)を上げて、山を仰ぐ気持ちになったのです。
(注2)セーレン・キェルケゴール(1813~1855年)
デンマークの哲学者、キリスト教思想家。抽象的な思弁より、個々の人間の存在の問題に光を当てた実存主義の先駆者といわれる。形式ばかりを重んじていたデンマーク教会の改革を訴えた。
我を助ける者
信仰とは「信じ仰ぐ」と書きますが、前向きに上を仰いで向上しゆく一筋の心、これを信仰といいます。行けども行けども、見渡す限り険しい山々が連なって、行く手をはばんでいます。しかも、巡礼者は進まねばなりません。
越えなばと思ひし峯に来てみればなほ行く先は山路なりけり
古歌
荒涼たる岩山が起伏していて、草木が一本もない地帯が、イスラエルの砂漠の地形です。「我、山に向かいて目を上ぐ。わが助けはいずこより」と、叫ばずにはおれません。
このような疑問に答えるように、一つの声が、「わが助けは、天地を造れるエホバ(主)から来る」と申しました。エホバとは、「実在の実在、在りて在る者」という意味です。天と地、大宇宙の存在する以前から実在してきたもの、これ天地を造りし神、エホバです。
人間は、はかなく弱いものでして、深い谷底を見ては、足がガタガタうち震い、険しい山路にさしかかると、足がすくんで歩けません。しかし信仰とは、神の力を杖(つえ)にして歩き抜いて、進みゆくことなのです。
一本の木立もなく、日中の温度は50度にも上る砂漠地帯があります。ひどい暑さの中、何かの保護がなければ、とても歩けません。ところが、「神が陰となって、右手の側(聖書では「右手」は力を表す)に立ってくださり、旅人をいたわり休ませてくれる」と詩人は申しています。神の御許(みもと)べは、まさに荒野のオアシス、水わく涼しい森に憩うような所です。このような表現は、あちらを旅行した者でなければわかりません。
私も、昔イスラエルの民をエジプトから引き連れて神の人モーセがさすらった、赤茶けたエドム(注3)の砂漠を歩きながら、峨々(がが)たるペトラ(注3)の岩山を踏み越え登ったり、シナイの山脈(やまなみ)を馬に乗って旅したりして皮膚は火ぶくれし、ひどい日射病にかかったりしました。いかに砂漠の太陽が強烈なものであるか。それで、涼しい朝か夜にしか歩けぬことがあります。
「我、山に向かいて目を上ぐ。いずこよりわが助けは」と叫ぶ巡礼者に対し、「エホバの神は、あなたのそば近くにやって来て、右手をおおう陰のようにしておられるから」と言って、この詩人は慰めております。

(注3)エドム、ペトラ
聖書時代は、現在のヨルダン王国領内の死海東岸から南のアカバ湾までの地域をエドムと呼んだ。紀元前2世紀ごろからこの一帯で栄えたナバテア人の都がペトラであり、今も遺跡が残っている。
インマヌエルの旅
いずれの宗教でも、「どうしたら神の世界に、神の国に至ることができるだろうか」と、神への道を求めます。この宗教心を「道心」と言いまして、「道心堅固」などと言ったりしますが、キリストの宗教は、神の道を求めながらも、道を求めることを断念する経験、これが大事なのです。学ぶだけでなく、インマヌエル、神と共に歩く経験を通して絶学(学びを究めて、それを超えた境地に入ること)することこそ、信仰の奥義なのです。
イエス・キリストの弟子が「主よ、どこに行かれるのですか、私はその道を知りたい」と言いましたら、キリストは「わたしは道である、真である、生命である。だれでもわたしによらないでは、父なる神の御許に至ることはできない」(ヨハネ福音書14章6節 私訳)と言われました。何かの道を求めることではなく、道であり、真であり、生命そのものであるところのキリストと共に歩く経験、これを信仰というのだ、とお教えになりました。
神学書や教義論の本を読んで、神に至る道を学んで知ろうとする神学者先生のように福音を思うならば、とんでもないことです。キリストは、「どうして、わたし自身を求めないのか、わたしを知ってくれないのか」と今も嘆いておられます。
神の人モーセが、出エジプトの途中、行き詰まって「願わくば、あなたの道を示してください」と訴えましたら、神は何と答えたもうたか、「わたし自身が、モーセよ、おまえと共に行くであろう」と。原文では「わたし自身」ではなく「わたしの顔 パナイ」と、強い表現になっていますが、神ご自身の顔がじっとモーセを見つめながら、昼は雲の柱となり、夜は火の柱となってでも一緒に旅を続けよう、と言われたのでした。四国のお遍路さんが目には見えないけれども弘法大師と一緒に歩くことを「同行二人(どうぎょうににん)」といいますが、同行二人、一人でいて一人でない経験──これが幕屋的信仰人の歩み方です。
行く末を遠くまで、遠い道を知らずともよい。一歩一歩、神ながらに、見えない神と偕(とも)に歩けるならば、それで十分です。
たとえば、見知らぬ所へ初めて行く場合に、地図やガイドブックを手引にして行くよりも、詳しいガイド、よき案内人が一緒について来てくれたほうが、どんなに心強く安心かわかりません。ましてや、天と地とを支配したもう神ご自身が、右の手をおおう陰のようにも、暑い日盛りの中も共に旅してくださるというのならば、道なき道をも突き進んでゆくことができます。
信仰は、冒険を恐れぬ心。
恐れる間は、神の御愛はわからない。
思い切り、未知の世界に歩いてゆこう。
私の前には道がない。
歩いた後から、道が作られてゆく。
未知の、果てしない野分け。
無辺際の神の御愛が、さし招いている。
思い切り未知の荒野を野分けして、神と偕に歩いてみようではありませんか。一足一足を導きたまえ、と祈りつつ。
(1972年)
本記事は、月刊誌『生命の光』851号 “Light of Life” に掲載されています。